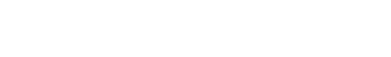第103期部門長 赤坂 大樹 (東京科学大学)

この度,第103期日本機械学会機械材料・材料加工(M&P)部門の部門長を拝命いたしました東京科学大学の赤坂大樹です.山崎泰広 副部門長(千葉大学),荒尾与史彦 部門幹事(早稲田大学)をはじめ,部門運営委員の皆様,広報および各技術委員会の委員の皆様,学会事務局の近藤愛美様のご協力頂きながら,本年度の部門運営を円滑に進めていければと考えております.
今から13年前の2012年に第8技術委員会の委員を努めましたのが,本部門との最初の縁でした.当時は35歳の所謂,“若手”でしたが,気付けば既に13年に渡り,本部門にお世話になって参りました.その頃は先輩委員の方々がスムーズに委員会を差配され,本部門の活動を円滑に運営され,羨望のまなざしで見ておりました.その頃は議論や運営に付いていくのがやっとでしたので,まさか部門長を仰せつかるとは,その時は夢にも思いませんでした.今でもこれまでの部門長の皆様の様なスマートな運営は小職にはできませんが,不器用ながらに尽力・努力をし,本部門の円滑な運営に努めて参りますので,何卒,よろしくお願い致します.
さて,本年は部門主催の国際会議の年であり,2022年にまだ、コロナ感染症の影響の社会環境におきまして沖縄で開催され,大変盛況に行われました第1回に続き,第2回機械材料・材料加工国際会議2025(ICM&P2025)が11月3日(月)~6日(金)に米国領グアムのHilton HOTELS & RESORTS, Guamで開催されます.グアムは直行便で4時間弱の距離にあり,日本では寒くなってまいります11月でも夏の様に海水浴が楽しめる環境にあります.
更に今回の会議では感染症予防の観点から前回ICM&P2022では開催を見送りましたバンケットも開催すべく準備を進めております.機械学会の会員の皆様をはじめ,世界各国の機械材料および材料加工に関する皆様のご参加を,心よりお待ちしております.
さて,部門長への就任に際しまして,2つの視点から本部門の運営委員会および各委員会の委員を新しく若手研究者の皆様と産業界の皆様にお願いし,委員としてお迎えする事としました.これは若手や産業界の委員の部門運営に携わる委員が近年,減少しております為に委員にご就任に頂きました.まず,新人の若手の先生方に委員就任をお願いしましたのは,若手研究者の部門活動への参画を促し,世代を超えた本技術分野の研究者の永続的なネットワークを形成して欲しいという考えに基づいています.13年前,私が本部門の第8技術委員会の委員を仰せつかりました時分,他では会うことができない御高名な先生方とも,お話をさせて頂く機会を得,それらがその後の自身の研究活動にも大きく貢献した経験があるためです.また反対に,新しい若手研究者の部門運営活動への参画は,新しい考え方を部門に齎し,従来にない新世代の機械材料・材料加工の技術領域を創生してくれる事も期待できます.このため,本年度の委員として新しい方をお迎えしました為,運営委員等の顔ぶれが変化しております.もう1つは企業の方の部門運営への参画を促すべく,企業の方へ運営委員としての参画をお願いしております.本来,工学系学会であります機械学会には産業界と学術界をつなぐ役割がありますが,近年,本部門の運営委員は大学をはじめとする学術界所属の委員が大半を占めておりました.更に,部門講演会などを鑑みましても,産業界からの講演件数は少なくなっており,これを改善し,産学連携の構築の場としての学会に再帰すべく,産業界の方に運営委員にご就任頂きました.これら,産業界の委員の皆様からのご意見等を取り入れ,学術と産業の橋渡しに本部門が貢献できる様に変革していく事を目指したいと考えております.これまで本部門を支えてきております皆様と新しい委員の皆様が齎す“新しい風“の相乗効果により,本部門が更に活性化して参りたいと考えております.
最後に本部門は材料と加工という産業の基盤を扱う部門であります.この為,他の分野や他部門と重複する領域も多く,これまでも講習会等を他部門と共催してきました.この様な学際領域では複数の学問的知見が必要であり,複数の領域が齎す他面的な視点方から新たな学問領域が創出される事も多々あります.一方で,この様な新領域の多くは大学等の教育機関では複数の領域をまたぐが故に,取扱いがない場合も多々あります.その様な,大学などでは難しい,新領域や学際領域の知見を得,自身で修得し,自身のスキルを向上する為に学会の講習会や講演会があると私は考えています.私自身,これまで材料を中心とした学際領域を歩み,電気→化学→機械の3つの領域を其々学んで参りましたが,学会の講演会等ではこれらを更に超える新領域の講演がなされ,特に部門講演会等では未だ新しい知見を得,ワクワクしながら帰路に就くことも珍しくありません.その様な“ワクワク”を皆様に提供できる講演会や講習会をこれからも開催し,会員の皆様に“ワクワク”を享受して頂ける様に運営して参る所存です.その上で,この1年間の部門長の役責を無事果たし,本部門の活性化に少しでもお役に立てたなら幸いで御座います.拙い運営となるかもしれませんが,部門登録会員各位のご支援,ご鞭撻を何卒お願い申し上げます.